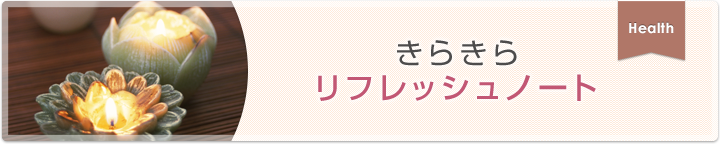動物とのふれあいから生まれる
癒やし効果とアニマルセラピー
気分が落ち込んでいるとき、犬や猫などの動物とふれあうことで気持ちが楽になったり、癒やされたりしたことはありませんか? 人類と長く一緒に暮らしてきた、犬をはじめとする身近な動物には、セラピー効果があるといわれています。
ここでは、動物がもたらす癒やしの作用やそれを活用したアニマルセラピーについてご紹介します。
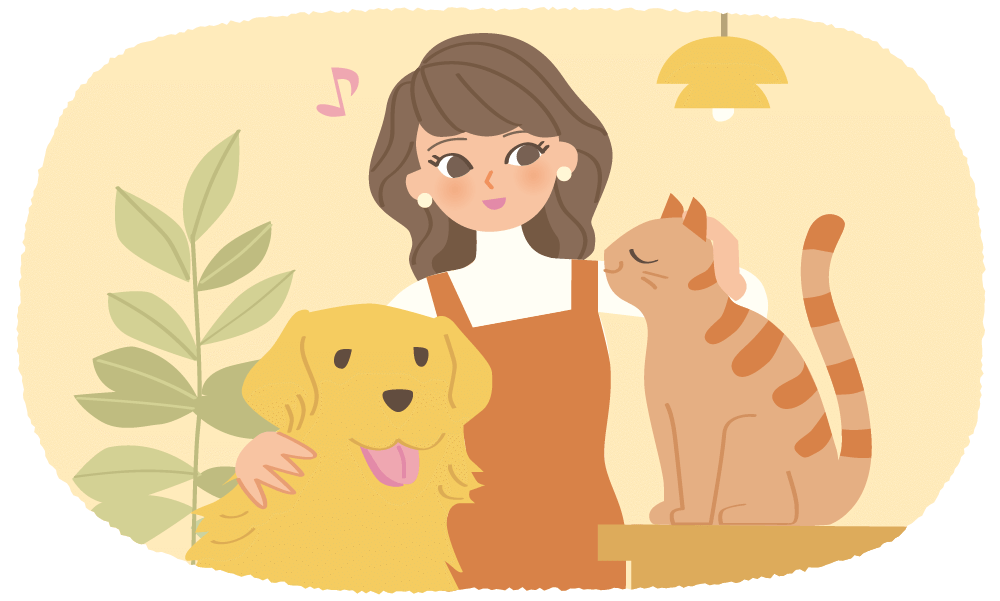
Point1
アニマルセラピーとは?
「アニマルセラピー」とは、一般的に適切な条件下で、適切な動物と接し人の心や体に様々な効果をもたらすことの総称として汎用されており、その内容は大きく3つに分けられます(人と動物との相互作用の正しい理解を促進する国際会議により定められ、国際会議にて運用されています)。
世界の人と動物の関係に関する国際組織International Association of Human-Animal Interaction Organizationsの基準によって以下のように定められています。

一つは「動物介在活動(AAA:animal assisted activity)」。例えば高齢者施設などに、ボランティア活動として適切な犬や猫を伴って飼い主さんなどが訪問し、動物とふれあうことで高齢者が生き生きとして笑顔になったり、自ら行動を起こすきっかけとなったりすることです。また、厳密にいえば“治療”ではありませんが、自宅やドッグカフェ、猫カフェなどでペットの動物とふれあい癒やしを得ることも、人それぞれ差はありますが、効果が望まれます。
さらに、人の治療に健康で適性のある犬たちや馬を伴って治療効果を目的とする「動物介在療法(AAT:animal assisted therapy)」や、小学校において動物(主に犬)を活用した授業などを行う「動物介在教育(AAE:animal assisted education)」などです。日本動物病院協会のプログラムには、「犬と仲良くなろう」や犬に本を読み聞かせることで、子どもの読書力をサポートする「犬との読書プログラム」などがあります。
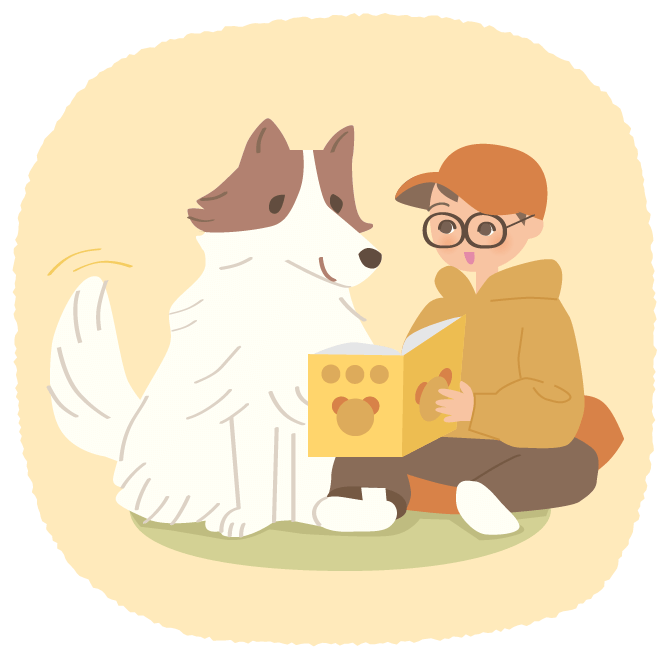
Point2
アニマルセラピーで幸せホルモンが出る!?
共に暮らす大切な動物の顔や動きを見たり、ふれあったりすると、笑顔になったり気持ちがリラックスしたり幸せな気持ちになったりしませんか? ペットを飼っている人、動物好きな人なら誰でも経験があるのではないでしょうか。「動物には癒やし効果がある」といわれますが、それは感覚的な表現だけではなく、科学的な根拠があることが証明されています。
正しい教育を受けたフレンドリーな犬、家族の一員である大好きな愛犬などとふれあうと“幸せホルモン”と呼ばれる脳内ホルモン、オキシトシンが分泌されることがわかっています。オキシトシンは、疲れやストレスを癒やし、多幸感をもたらしてくれる作用があります。例えば、日本動物病院協会(JAHA)の活動でセラピー犬が訪問した、千葉県こども病院小児血液・腫瘍科病棟において、患者(子ども)、セラピー犬、ボランティア(飼い主)に対して、セラピー犬とのふれあい前と後の唾液を調べたところ、ふれあい中にオキシトシンが増加し、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールの値が下がっていたことがわかりました※。さらに、この検証では、訪問を受けた子どもたちだけではなく、セラピー犬自身とその飼い主であるボランティアにも同様の効果が見られたのです。
※千葉県こども病院、日本動物病院協会、東京農業大学 太田光明先生による訪問検証より
Point3
アニマルセラピーには信頼関係が大切
では、動物であればどんな種類でもアニマルセラピーが可能だったり、癒やし効果があったりするのか?というと、そうではありません。アニマルセラピーに適しているのは、犬や猫などのいわゆる伴侶動物。長い歴史の中で、人間と親密な関係を築いてきたことが大切です。家族や子どものような立ち位置で暮らし、幸せを分かち合う存在として接してきた動物だからこそ、“癒やし”を与えられる存在なのです。約1万2千年前のイスラエルの遺跡では、人の遺体の手が子犬の遺体の上に置かれる形で一緒に埋葬され、その親密な関係が見てとれます。そういう意味では、馬やモルモット、ウサギといった動物も、犬や猫ほどの歴史はありませんがその範疇に入れることができるでしょう。
最近は、ヘビやトカゲなどのエキゾチックアニマルを飼われる方も多いですが、人との共通感染症などもクリアされていないことや、その動物に適した生活環境を維持するのが難しいこと、また信頼関係を築くことも困難ですから、アニマルセラピーには向いていません。
Point4
飼い主もペットも幸せになる暮らし方を
『なぜ犬と暮らす人は長生きなのか』(谷口優著/エクスナレッジ)という本があります。「犬と一緒に暮らすと、健康で長生きができる」という内容ですが、これは決して大げさではありません。犬と暮らしていたら、朝晩散歩に行って規則正しい生活になり健康維持が期待できますし、外に出かけることで他人とのコミュニケーションの機会も増えるでしょう。犬だけに限らず、室内で暮らす猫や他の小動物なども、決まった時間に起きて食事を用意したり、運動させたりといったことは必要ですので、動物と暮らすことで規則正しい生活が送れることは間違いないでしょう。
また「ペットに癒やされたい」と思う人は、まず身近な動物に人と同じく家族のように愛情を注いで育て、幸せにしてあげることが大切です。いくらペットと暮らしていたとしても、世話やしつけもせず、信頼関係を築いていなければ癒やしを育むどころか苦痛が生じてしまいます。愛情をもって育てられ幸福感のあるペットは、ペット自身だけでなく周囲も幸せにしてくれます。ペットと暮らすことを迷っている方は、ぜひ犬や猫などの動物と日常的にふれあい、癒やしを得られる生活を始めてみてはいかがでしょうか。

監修
柴内 裕子(しばない ひろこ) 獣医師・赤坂動物病院 名誉院長
1963年に赤坂獣医科病院(現赤坂動物病院)を開設。1981年に日本動物病院協会(JAHA)第4代目会長就任。人と動物のふれあい活動CAPP(コンパニオン・アニマル・パートナーシップ・プログラム)をスタート。小児病棟、小学校、高齢者施設などに動物たちと共に訪問する活動を35年以上続ける。日本におけるアニマルセラピーの先駆者である。著書に『猫は友達』(NHK出版)、『子犬がわが家にやってくる』(講談社)などがある。
赤坂動物病院 https://akasaka-ah.com/